
横浜美術館の開館20周年記念展「フランス絵画の19世紀展」に行ってきました。
コンセプトは、美をめぐる100年のドラマ。
この100年のドラマを概観すると、
18世紀後半、普遍的な理想美を追求する新古典主義(代表:ダヴィッド)が、簡素で厳格な画面構成と力強く緻密なデッサンで前時代のロココ趣味を払拭。
その後、1820年~1830年にかけて個人の感性を重視するロマン主義(代表:ドラクロア)が台頭。
これら新古典主義とロマン主義の特徴を併せ持つ中庸派(ジュスト・ミリュー)が歴史画を親しみやすく現実感に富んだ手法で描く歴史風俗画を創始。
19世紀には、現実を生きる民衆をありのままに描くレアリズム(代表:クールベ)が勃興。
古典主義に固執する美術アカデミーの権威は揺らぎ、歴史画と風俗画の境界はますますあいまいに。
印象派が隆盛するに及び、グループ展などが頻繁に行われるようになると、それまで公に作品を問うことのできる唯一の場「サロン」は改組され、国家主権から民営の「フランス芸術家協会」主催のサロンへ、そして、1891年には、「フランス芸術家協会」が分裂してできた「国民美術家協会」主催のサロンへ、さらに、1884年、「独立美術家協会」によるアンデパンダン展が開催。
これら芸術の民営化の動きが、後期印象派や象徴派など革新の動きを促進し、20世紀絵画の展開につながる…
展覧会の構成は4章構成。
章タイトルと印象に残った作品は以下。
第1章アカデミズムの基盤―新古典主義の確立
『アキレウスの怒り』ミシェル=マルタン・ドロリング
『男性裸体習作』または『パトロクロス』ジャック=ルイ・ダヴィッド
『エンデュミオンの眠り』アンヌ=ルイ・ジロデ=トリオゾン
『ヒュラスとニンフ』フランソワ・ジェラール
『パフォスのヴィーナス』ジャン=オーギュスト=ドミニック・アングル&アレクサンドル・デゴッフ
第2章アカデミズム第一世代とロマン主義の台頭
『アブラハムに追放されるハガル』エミール=ジャン=オラース・ヴェルネ
『青の寓意』または『ナポリ近郊、アルコの聖母礼拝堂の祭りからの帰り道』レオポルド・ロベール
『クロムウェルとチャールズ1世』イポリット・ドラロッシュ(通称ポール・ドラロッシュ)
『パリ国立美術学校の半円形講堂壁画のための原画』同上
『ロキュスト(プリタニキュスに使う毒薬をロキュストがナルシスに渡し、若い奴隷にそれを試す)』グサヴィエ・シガロン
『死せる娘を描くティントレット』レオン・コニエ
『トロイアへ向かうギリシャ軍の動きを見張る、プリアモスの息子ポリテス』イポリット・フランドラン
『ウジェーヌ・ウディネ夫人』同上
『預言者エレミヤ』アンリ・レーマン(本名カール=エネルスト=ロドルフ・ヘンリッヒ)
『オダリスク』ジャン・ジャラベール
第3章アカデミズム第三世代とレアリズムの広がり
『アベルの死体を見つけるアダムとエヴァ』ジャン=ジャック・エンネル
『黄金への欲望』トマ・クチュール
『ヴィーナス誕生』アレクサンドル・カバネル&アドルフ・ジュルダン
『真珠と波』ポール・ポードリー
『弟子にベルヴェデーレのトルソを見せるミケランジェロ』ジャン=レオン・ジェローム
『寄ったバッコスとキューピッド』同上
『フローラとゼフュロス』ウィリアム=アドルフ・ブグロー
『牧歌』ジャン=ジャック・エンネル
『幻想』ピエール・ピュヴィ・ド・シャヴァンヌ
第4章アカデミズム第四世代と印象派以後の展開
『へべ』カロリュス=デュラン(本名シャルル=エミール=オーギュスト・デュラン)
『海を見る少女』フェルナン・コルモン(本名フェルナン=アンヌ・ピエストル)
『フロレアル(花月)』ラファエル・コラン
『犬を連れた婦人』または『エルネスト・フェドー夫人の肖像』カロリュス=デュラン(本名シャルル=エミール=オーギュスト・デュラン)
『エリーズ嬢の肖像』ラファエル・コラン
『干草』ジュール・バスティアン=ルバージュ
『エジプト逃避途上の休息』リュック=オリヴィエ・メルソン
この100年の絵画の流れを私なりに端的に言うと、
マッチョ(新古典主義)からセクシー(レアリズム)へ、そしてエコ(印象派)へ
となります。

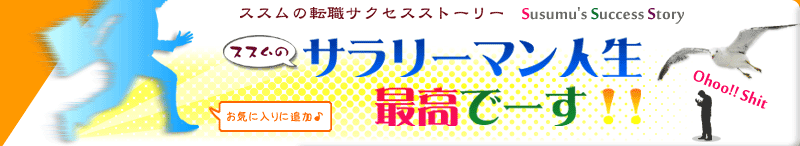





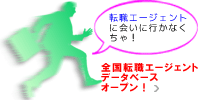



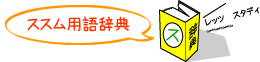
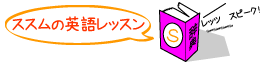
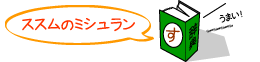
コメントする
トラックバックする
トラックバック用URL: