能力主義と言われた時代もあった。
みんなスキルをつけようとビジネススクールに通ったりして自己研鑽に努めたものだ。
努力すれば成果が得られることもあったが、そうでないこともあった。
それは結局能力の有無として片付けられた。
能力の無い者は詮方なく、泣き寝入りするしかなかったのだ。
21世紀も半ば過ぎ。
いまや、ビジネスに必要な能力はすべてサプリメントで補える時代となった。
コミュニケーション力は「ビタミンCo」、協調性は「ビタミンHa」、交渉力は「ビタミンNe」、企画力は「ビタミンPl」、柔軟性は「ビタミンFl」、プレゼン力は「ビタミンPr」、などという具合だ。
「あなたは、ちょっとコミュニケーション能力が欠乏しているから、ビタミンCoを摂取したほうがいいですよ。あと、企画力を伸ばすために、ビタミンPlを処方しておきますね」
年に一度の能力査定の席で、社内クリニックの勤務医ドクター・キムラは、同社でプランナーを務めるササキを診療して言った。
ササキは入社当初は、コンペの勝率で同僚に大きく水をあけられていたが、いまや彼らと肩を並べる好成績を収めるに至っている。
それもこれも、すべてはつい2年前に発明された「能力アップサプリ」のおかげなのだ。
「ササキさん!受注決定です!」
コンペ結果を告げる営業の声に、ササキと同期入社でこれまでトップをひた走ってきたヤマダは影で臍を噛んだ。
受注成績でササキの後塵を拝するという屈辱。
「これもすべてササキさんのプレゼン力が相手を凌駕したからですよ!」
こんな会話がなされた3年後、「プレゼン力」や「交渉力」「企画力」などの言葉は最早死語と成り果てていた。
それらの能力は誰もが等しくサプリで高められるばかりか、どんな者でも最高度まで高められ、しかも各人でその差が一切ないということが判明したからである。
脳の活動を司るニューロンの数は個人によって差はなく、その数はおよそ一万個である。
ニューロンがシナプスを介してネットワークを作る際、出来上がる組み合わせの数は、サプリでみな等しく最大数まで高められる。
ニューロンの活動を補助するグリア細胞は初期状態では人それぞれだが、サプリの作用で等しく増加させることが可能になった。
つまり、殊知性にまつわる活動に関する限り、サプリを飲めば誰もが同程度の能力を獲得できるというわけだ。
誰がやっても誰が考えても、サプリで最高度の能力に達している者なら、同じ成果を上げることができるのだ。
だから、コンペが実施されても、各社の提案はまるでコピーしたように同内容であり、またプレゼンのインパクトも同程度に高いのである。
商品やサービスの開発力もまた然り。
どの会社のどの社員も等しく高度な能力を有しているから、同時多発的に類似の商品・サービスが市場に登場する。
それを提示された消費者は同じような機能・デザインの商品の前でどれを選べばいいのか右往左往するのである。
では、仕事上の優劣は何をもってはかられるようになったか。
体力と持久力、瞬発力である。
運動に関わるニューロンは脊髄の中にある。
脊髄の中の上位運動ニューロンが脳から受けた指令を下位運動ニューロンに伝え、さらに下位運動ニューロンが筋肉、血管、腺組織、臓器に連絡することで運動は起きる。
脳内ニューロンの活動が活発だからといって、運動神経が発達しているとは限らない。
サプリは知的活動には有効でも身体活動に関しては全くの無力なのである。
上位運動ニューロンと下位運動ニューロンとの連絡をスムーズにし、脳からの指令を早く身体の各部位に伝える方法はこの時代にもまだ未解明のままだ。
運動能力の向上は目下個人の努力以外しかない状況なのだ。
いかに早く移動できるか、いかに長く働き続けることができるか、いかに早く対応できるか、いまやこれが相対評価の対象である。
筋肉主義の時代が到来したのだ。
消費者がどれを買おうか迷っていたらいち早く自社の製品を差し出す。
求められれば、商品を快く家に送り届ける。
消費者がいつでも買いにこられるように365日24時間営業するのは当たり前。
一箇所に止まっている暇はない。
夜であろうが、大雨であろうが、戸外に出て、大声で大々的に自社の商品・サービスをPR。
ときに、ビルの屋上から飛び降りることもあった。
自殺すると見せかけ、ビルの下に群集を集めておいて、広告の掲載されているパラシュートが開いたときに、多くの人々の目に自社広告を印象付ける手法だ。
ライバル会社を蹴落とすために日夜街中で暴力行為が頻発した。
オフィスの光景は一変した。
かつては仕事に欠かせぬツールとして重宝されていたパソコンや電話機はオフィスの隅に追いやられ、代わりに、トレーニングベンチやスクワットスタンド、レーサースピンバイク、サンドバッグ、ベルバッグ、パンチングボール、トレッドミルが立ち並ぶこととなった。
社員たちはダンベルで上腕二頭筋を、腹筋で腹直筋を、スクワットで大臀筋を鍛えまくった。
オフィスの隅の電話が鳴ると、一斉にそちらにスタートダッシュをかけ、誰が一番に受話器を取るかが競われた。
電話に出るスピードと回数が次の能力査定で評価され、給与に如実に反映されるのだ。
女性が出世する道はほぼ断たれたと言ってよい。
顧客に送り届ける荷物は専ら社員が自分で走って届けることにより、対応力をアピール。
打ち合わせがあれば、請われもしないのにわざわざ出向いて、顧客を背におぶり、自社ビルのミーティングスペースにご案内。
デスクにイスはなく、パソコンを使う場合はみんな空気いすで1、2時間はざらに作業する。
いまや、社員が握っているのはペンでもマウスでもなく、ハンドグリップだった。
ヤマダは再び自分の時代が来たと小躍りした。
彼は学生時代ラグビーで腕を鳴らした名ラガーマンだったのだ。
どんなキツいトレーニングにも馴れていた。
一方、ササキはからきし駄目だった。
彼は文化系だったため体力がなかった。
取ろうとした電話はことごとく他の社員の手に落ちた。
「どうしたんだ?最近全然成績が上がらんじゃないか」
上司のハヤシが昼食の席で腕組みして言った。
ササキは言葉もなくただうなだれるほかなかった。
彼はその足でビルの2階に行くと、クリニックに入った。
ドクター・キムラに相談すると、彼はいたずらっぽい笑みを浮かべながら言った。
「なるほど。私にできることと言えば、君にクスリを処方してあげることだけだ」
「何かいい方法はないですか?」
「ないこともないんだが……」
ドクター・キムラは含みのある言葉を残して黙り込んだ。
「先生、お願いします」
ササキは彼にすがり付いた。
「君は人としての魂を失う覚悟があるのかね?」
「はい!」
ササキは即答した。
「じゃあ、あなただけ特別ですよ。私は弱い者の味方ですから」
キムラはササキから100万円をキャッシュでもらう約束を取り付けてから言った。
自動販売機が動いていると思ったら、後ろでササキがものすごい形相で動かしているのを見たと言う。
逆立ちしながら小便するのを見たと言う。
ササキは見る見るうちにいかつい体つきに変貌した。
ササキほど人間の生活からかけ離れた人間はいないだろう。
他の者は24時間不眠不休とは言え、密かにトイレの個室で水浴びをしたり、仮眠を取っていたりしていたのだが、ササキは寸毫もそのような気配を見せることがなかったのだ。
それに対抗しようとする者がいた。
ヤマダである。ヤマダは社内でササキと会うと、静かに右手を差し伸べた。
ササキはそれを見て、同じく右手でガッシリとそれを掴んだ。
傍目には親しげに握手をしているように見えた。
しかし、よく見ると、ふたりの額に大量の脂汗が流れているのが分かるはずだ。
互いに渾身の力を込めて手を握り合っている。
どちらも一歩も引こうとはしない。
ふたりの周りには、トレーニングを一旦休止して、宿命の対決を見届けようとする人だかりができていた。
遠くで電話が鳴っているが、みんな勝負の行く末に意識を集中しているため、全然気づかない。
見詰め合う目は憎しみで充血し、握り合う手には青い血管が浮き出ている。
ボキボキボキィ。
「うがあ!」
ヤマダは苦悶の表情を浮かべ、必死で手を離そうとした。
しかし、ササキの手はいっかな離そうとしない。
ボギボギボギ。
「ぬがあ!」
ヤマダはその場に崩れ落ちた。
それを見ると、ササキは蔑視を投げかけて、去って言った。
後に残されたヤマダは床に俯きながら奥歯をギリギリ鳴らしていた。
「くそう、くそう、くそ!」
そう言って誤って負傷している右手を床に叩きつけ、激痛のあまり失神した。
床に放置されていたヤマダは数分後には目を覚まし、今の屈辱を頭の中で反芻して心に誓った。
ササキを殺そうと。
ヤマダは負傷した右手のリハビリを続けながら、復讐の機会が訪れるのを虎視眈々と待った。
意外に早くそのときはやってきた。
ヤマダは、ササキが出勤するとき、階段もエレベータも使わず、ビルの壁を這い上がって、一旦屋上に着いてからオフィスのある6階に下りてくるということを聞いて、これだ!と思った。
チャンスはそのときしかないと思った。
次の朝、ヤマダは誰よりも早く出勤した。
そして、静かに屋上まで上ると、フェンスを越え、絶壁の縁に腰掛けた。
眼下では、人々が蟻んこのようにせかせかとビルに入っていくのが見える。
それから数日後、会社の人々はササキが非常階段を1階から20階上の屋上まで朝から晩まで往復するのを見たと言う。
その中に、明らかに他の人と違う風体の男が混じっていた。
ササキである。
ササキはビルの入り口へは向かわず、ビルの裏手に回ると、やおら両手を壁につけ、ヤモリのように壁を登り始めた。
チョークバックも背負わず、ハーネスもつけず、規則正しい手足の動きで、ズンズン登ってくる。
ヤマダは手に持っていたビンのキャップを外すと、壁沿いに液体を滴らしはじめた。
液体は壁を伝い、壁に吸着するササキの左手に流れた。
その瞬間、ツルっ。
左手が壁から離れ、彼の身体はバランスを失った。
彼は右手を壁に吸着させることでかろうじてその位置に止まりながら、手に付いた液体の臭いを嗅いだ。
それはオリーブ油の臭いだった。
「くそっ!」
ササキもヤマダも同時に舌打ちした。
ヤマダはササキを壁から転落させようと、ビンの中の油をありったけササキ向かって注いだ。
ササキは流れくる油を全身で受けながら、右手を壁から離すまいと、両目を固く閉じてグッと堪えた。
「畜生!」
ヤマダはササキがなかなか転落しないことに苛立ちを募らせた。
「こうなれば、アレしかない!」
彼は突然駆け出し、屋上から一階に下り、ササキの真下にやってきた。
そして、懐からライターを取り出すと、壁に流れる油の筋に点火した。
火は見る見るうちに壁を這い登り、ササキの身体を包み込んだ。
「うぎゃあああ!」
ササキは獣のような悲鳴を上げて、蜘蛛のような素早さで壁を駆け上がった。
屋上まで着いたササキは、火達磨になりながら、階下のトイレに駆け込み、便器に頭を突っ込んだ。
シュー、シュー、シュー……。
便器から頭を上げたササキの顔は焼けただれ、最早往時の面影は微塵もない。
ちょうど入ってきた人が、便器に火を噴く人を見、急いでバケツに水を汲んで消火に当たった。
すぐに救急車が呼ばれ、ササキは緊急手術を受け、奇跡的に一命を取り留めた。
恐るべき回復力によって、3日後には通常業務に復帰できるまでになった。
ただし、その姿は、全身包帯ぐるぐる巻き、フランケンシュタインのようである。
「しかし、よくぞ屋上まで火達磨になりながら壁を這い登ったものだ」
部長であるハヤシはササキの無謀を責めるどころか大いに褒め称えた。
こういう我が身を顧みぬ行為こそが、今後顧客満足度の向上に繋がると信じて疑わなかったからだ。
それを聞いて、みんなやんやの喝采をササキに送ったが、ひとりだけ苦虫を噛み潰したような顔でその様子を横目で見ている者がいた。ヤマダである。
彼は、自分のしたことが結果的にササキの評価を高めたことが悔しかった。
ササキよりもすごいことをやってのけて、社内の評価を高めなければと思った。
「おれはもっとすごいことをやります!」
ササキを囲んで和気藹々と語り合っていた社員たちの目が一斉にヤマダに向かった。
「おれはそんな奴よりもっとすごいことができます」
ハヤシは静かにヤマダに歩み寄ると、「ほう」と嘆声を発し、手を顎に当てた。
「何ができるというのかね?」
面と向かって尋ねられたヤマダは一寸たじろいだが、ままよという気持ちで言ってのけた。
「おれはビルの壁を、上から下に下ることができます!」
社内にどよめきが起こった。
「おー!」
誰かの歓声で一気に喝采が起こった。
「いいぞー、ヤマダ!」
こうしてヤマダはビルの壁を屋上から一階まで下ることとなった。
できるだろう、というのがヤマダの目算だった、しかし、実際に屋上の縁に立ってみると、屈んで手を壁に付けるのさえ困難であると判明した。
下では社員たちが固唾を飲んで自分のチャレンジを見守っている。
後に引くことはできそうにない。
こうなったらもう死んでもやるしかない、と両手をビルの壁に付けて、ヤモリのように壁を這い下ろうと足を宙に蹴り上げた瞬間、ヤマダの身体は急転直下、地面めがけて落下をはじめた。
「だああああ!」
下で見上げていた人々は自分のところに勢いよく落ちてくる物体を避けようと、後ずさった。
人だかりの中にぽっかりと大きな穴ができた。
ベシャ!
その真ん中にヤマダは頭から激しく突入した。
救急車が呼ばれ、緊急手術となった。
全身を強打し、強度の脳震盪を起こしているものの、命に別状はなかった。
芝生と柔らかい土が衝撃を吸収したのではないか、というのが医者の意見だった。
ヤマダは恐るべき生命力によって、3日後には退院を許され、通常業務に復帰したが、その姿はやはりフランシュタインだった。
全身包帯に巻かれているからササキもヤマダも区別がつかなくなった。
「おい!ササキ」
午後のひととき、トレッドミルの上を歩行するハヤシから声が上がった。
その声に反応する者は誰もいなかった。誰もが自分のトレーニングに余念がなかった。





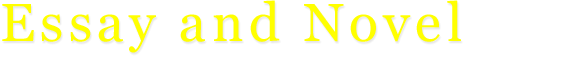
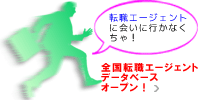






コメントする
トラックバックする
トラックバック用URL: